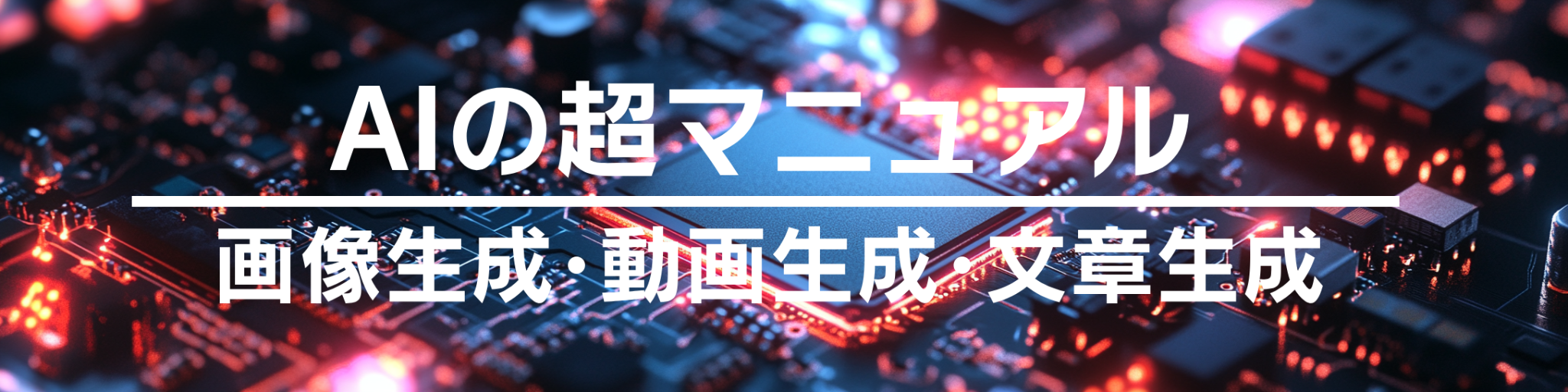その他
その他 世界初の人工知能:ロジック・セオリスト
1950年代、コンピュータ科学はまだ発展の初期段階にありました。コンピュータは主に計算を高速に行う機械として認識されており、人間の知能を模倣するという発想は、一部の研究者の間でささやかれる程度でした。そんな中、アラン・ニューウェル、ハーバート・サイモン、クリフ・ショーらによって開発された「ロジック・セオリスト」は、世界に衝撃を与えました。「ロジック・セオリスト」は、数学の定理を自動的に証明するプログラムでした。これは、それまで人間だけが扱えると考えられていた抽象的な思考を、コンピュータが初めて実行したことを意味します。このプログラムは、記号論理学という数学的な体系を用いて、人間の論理的な思考プロセスを模倣していました。そして、実際にいくつかの定理を証明してみせたことで、「人工知能」という言葉が初めて用いられるきっかけとなりました。「ロジック・セオリスト」の登場は、単に新しいプログラムが開発されたという以上の意味を持ちました。それは、機械が人間の知能を超える可能性を示唆し、世界中の人々に大きな希望と同時に、大きな不安を抱かせました。そして、この出来事をきっかけに、人工知能という新たな研究分野が幕を開けたのです。