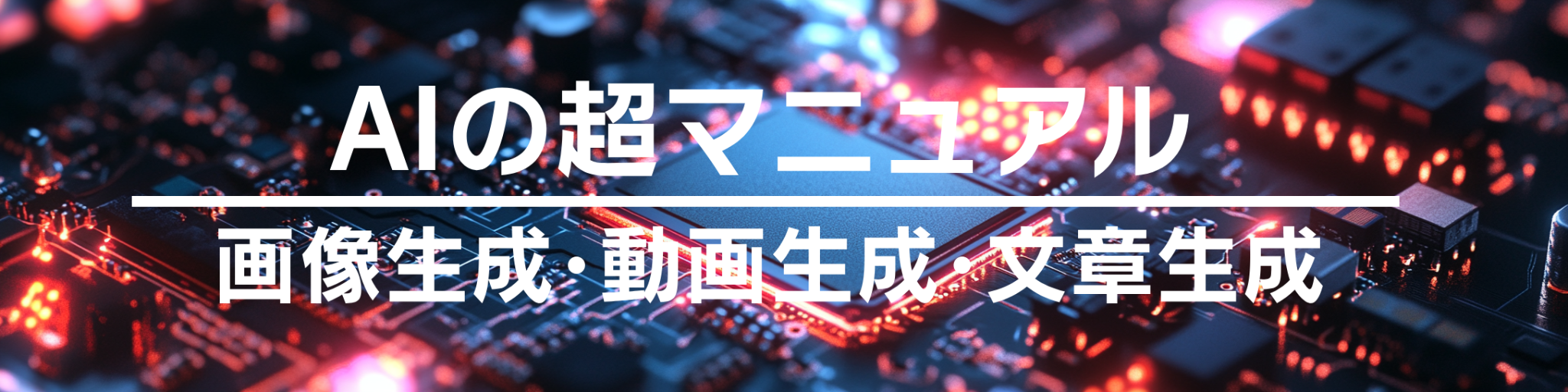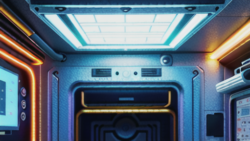アルゴリズム
アルゴリズム L0正則化:スパースなモデルを実現する技術
機械学習の目的は、与えられたデータからパターンや規則性を学習し、未知のデータに対しても精度の高い予測を行うことができるモデルを構築することです。しかし、モデル構築は複雑さと精度のバランスを取るという難題を伴います。
モデルが複雑になりすぎると、訓練データに過剰に適合してしまう「過学習」という現象が起こります。これは、例えるならば、大量の問題とその解答を丸暗記して試験に臨むようなものです。丸暗記した問題は完璧に解けても、少し問題文が変わったり、見たことのない問題が出題されると対応できません。
機械学習のモデルも同様に、訓練データに含まれる些細な特徴やノイズまで学習してしまうと、未知データに対しては正確な予測ができなくなってしまいます。これが過学習です。
過学習を防ぐためには、「正則化」という技術を用いてモデルの複雑さを調整します。これは、モデルが過剰に訓練データに適合することを抑制し、より汎用性の高いモデルを構築するための手法です。
正則化は、モデルの複雑さを表す指標にペナルティを課すことで、モデルの自由度を制限します。その結果、訓練データのノイズや特徴に過剰に反応しなくなり、未知のデータに対しても安定した予測能力を発揮できるようになります。
このように、機械学習においては、モデルの複雑さと過学習の関係を理解し、正則化などの技術を用いて適切にモデルの複雑さを制御することが重要です。