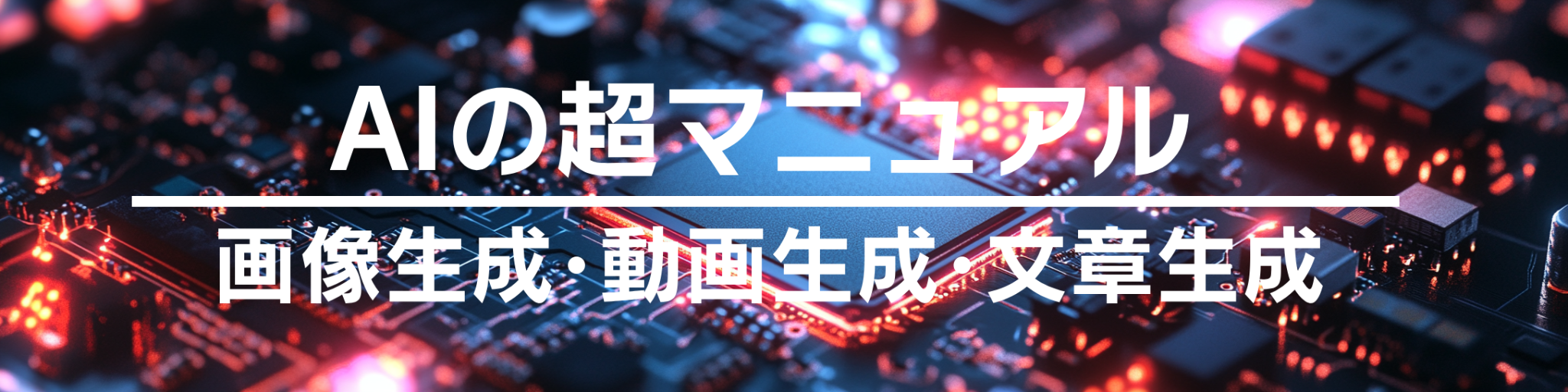アルゴリズム
アルゴリズム 探索と活用:バンディットアルゴリズムとは?
- はじめにと近頃では、ウェブサイトやアプリなど、私たちが日常的に利用するデジタルサービスの重要性は増すばかりです。こうしたサービスの多くは、膨大な量のデータを基に、利用者一人ひとりにとって最適な情報やサービスを提供しています。そして、その裏側を支えている技術の一つに、「強化学習」と呼ばれる機械学習の手法があります。
強化学習は、試行錯誤を通じて行動を学習していくという、人間の学習プロセスを模倣した手法です。コンピュータが仮想的な環境の中で試行錯誤を繰り返し、より良い結果を得られる行動を学習していくことで、複雑な問題を解決することができます。
今回は、数ある強化学習の手法の中でも、「探索」と「活用」のバランスを調整することで最適な行動を選択する「バンディットアルゴリズム」について解説していきます。バンディットアルゴリズムは、限られた情報の中から、最も効果的な選択肢を見つけ出すことを得意とするアルゴリズムです。例えば、ウェブサイト上での広告表示や、オンラインショッピングにおける商品推薦など、様々な場面で応用されています。